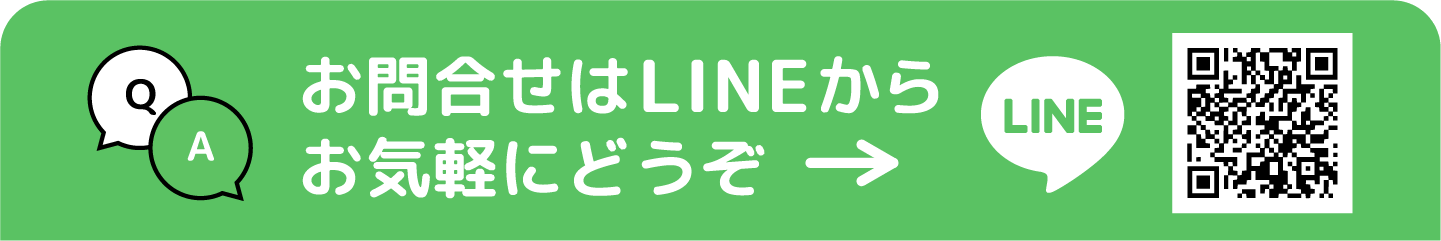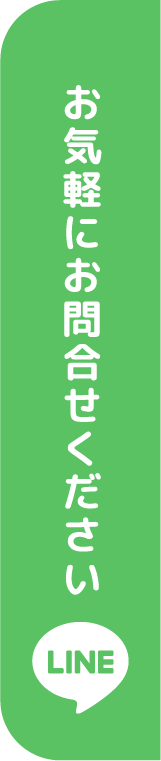「○○は何の役に立つの?」というフレーズは色々な学問に対して言われることですが、数学もその例外ではありません。
ただ、これについては、どちらかといえば数学は恵まれている方でしょう。工学・統計・金融などなど、数学が「役に立っている」分野は枚挙に暇がありません。方程式、三角関数、指数・対数、微分・積分……どれも「これなくしては現代の科学技術は立ち行かない」と言えるものばかりです。
対数や微分などは、実際に「役に立つ」という目的のために構築された理論と言ってもいいでしょう。対数を発明したネイピアは、対数を「複雑な計算を楽にするためのもの」と捉えていましたし、対数以外にも計算を簡単にするための道具を開発したりしています。ニュートンが微分法を作ったのは、力学の運動法則を記述し、物体の運動の予測を行うためでした。
しかし、数学が全て「役に立つ」ために作られたというわけではありません。むしろ、数学理論は、構築された当初は「特に何の役にも立たなかった」ものの方が多いくらいかもしれません。
ところが、そんな誰もが「現実の役には立たない」と思っていた数学理論が、突如として「役に立つ」場面が出てくることが往々にしてあるんですね。今回はそんな話をしたいと思います。
情報技術の基盤となった「型理論」
数学には、数学全体の論理構造を研究しようという分野があり、「数理論理学」と呼ばれています。
バートランド・ラッセルが生み出した「型理論」は、そうした分野における理論の一つでした。
ラッセルは普通の言葉で書かれた命題が論理的な矛盾を生じるという問題(パラドックス)を回避するため、命題の表現を全て記号で置き換え、矛盾を生じないように厳密な規則を与える理論を構築したんです。
ちょっと聞いただけでも、「現実の何かの役に立ちそうな話ではないな」と多くの人は思うはずです。ラッセル自身も、自分の理論が現実の世界で「役に立つ」とは全く思っていなかったでしょう。
ところが、コンピュータが発明され、様々なプログラミング言語が開発されるようになると、それが一変しました。
ラッセルの理論は、プログラミング言語の基本的な規則・文法を構築するのにうってつけの理論だったんですね。型理論は瞬く間にプログラミング言語の基礎を成す「型システム」として、情報技術の根幹を支える理論になりました。
ブラックホールからGPSまで、宇宙研究と技術の要「リーマン幾何学」
「幾何学」とは、図形の性質について研究する数学の分野のことです。中学校の数学の授業では、平面上の図形の性質や、公理・定理・証明などについて習いますが、これは「ユークリッド幾何学」と呼ばれる、数学のなかでも古くからある理論の一つです。
19世紀になると、平らな平面ではなく「曲がった面」での幾何学「非ユークリッド幾何学」が考案されました。この新しい幾何学は高次元に拡張され、「4次元の曲がった空間」のような、どう考えても現実には存在しなさそうな「図形」を扱う学問として発展していきます。ベルンハルト・リーマンが研究した「リーマン幾何学」は、このような「曲がった空間」における「長さ」や「曲がり方の様子」などを記述する理論でした。
この「現実の世界と何の関係もなさそうな図形の理論」を、現実世界にあてはめようとしたのが、有名なアルベルト・アインシュタインです。
アインシュタインは自分が生み出した「特殊相対性理論」を発展させて、ニュートンにかわる新しい重力の理論を作ろうとしていました。彼は数学者マルセル・グロスマンにリーマン幾何学について教わったのですが、そのときグロスマンは「物理学者が深入りするような理論じゃないよ」と助言したといわれています。
結果的に、新しい重力理論である「一般相対性理論」はリーマン幾何学を基盤として完成しました。「曲がった空間」は数学者の頭の中にしかない仮想的な存在ではありませんでした。私たちの生活している空間は、重力によって「本当に曲がっていた」のです。
一般相対性理論は、ブラックホールの存在や宇宙の歴史など、人類の宇宙に対する捉え方をがらりと変える重要な理論になりました。地球の重力による時空間の歪みを補正するために、GPSの計算にも使われています。
3D時代になって脚光を浴びた、忘れられていた理論「四元数」
高校の数学で扱う「複素数」と呼ばれる数の体系があります。二乗したら-1になる数を虚数単位「i」として、2つの実数の組み合わせで表されます。
z=a+bi
複素数が何の役に立つのか分からない、という高校生の皆さんは少なくないかもしれません。(複素数は交流電流の理論や量子力学などの物理理論に幅広く使われています。)
これをさらに4つの実数の組にして、新たな数の体系を作ってしまった人物がウィリアム・ハミルトンです。
q=a+bi+cj+dk
ハミルトンは、「虚数単位」を「i, j, k」と3つに増やして、こんな数を作りました。これを「四元数」と呼びます。この四元数は、複素数と違って、実数の計算法則を完全には満たしてくれません。かけ算の交換法則が成り立たないんです。
p×q≠q×p
四元数は当初、3次元空間の力学の研究などに応用されていたんですが、便利な「ベクトル」という表現法にとってかわられ、あまり使われなくなっていきました。
ところが、宇宙技術とCGの発展が、四元数を再び表舞台に立たせることになります。
四元数は、立体の3次元空間での回転を表現するのに非常に優れた理論だったんですね。簡単な計算をするだけで、「物体がどの軸を中心にどれだけ回転したらどの方向を向くのか」がすぐに分かるんです。
そのため、四元数はロケットや人工衛星の姿勢制御の計算に重宝されるようになりました。さらに、複雑な3DのCGの動きをプログラミングする方法としても普及し、動画全盛の現代を支える基盤の一つになっています。
「役に立つかどうか分からない」ということ
これら3つの理論はどれも、作られた当時に「この理論がこんな風に役に立つ」と予想するのは不可能だったでしょう。コンピュータのない時代に、プログラミング言語への応用が予想できるはずがありません。
数学理論に限らず、「今研究していることが将来どのように役に立つのか」を予想するのは非常に難しいことだと言えます。社会の未来がどうなるかは誰にも分からないからです。
「役に立つかどうか分からない」研究をなぜ行っているのか。それは人によってそれぞれでしょう。ただ一つ言えることがあるとすれば、それらは皆、(大袈裟に言えば)世界において「これまで見えなかったものを見えるようにする」、あるいは「世界を広げようとする」試みだということです。
ここまで「社会において数学理論が役に立つかどうか」の話をしてきましたが、「個人にとって、勉強が役に立つかどうか」についても同じことが言えます。
今の勉強が将来何の役に立つのか、という問いはやはり本質的にとても難しいのです。個人の未来がどうなるかも、社会の未来と同様、誰にも分からないからです。
そして、個人にとってもやはり「勉強すること」の意義の一つは「世界を広げようとすること」だと言えるでしょう。役に立つかどうかは分からないけれど、もしかすると役に立つかもしれないときのために「できるだけ世界を広げておく」ということです。
この文章を読んでいる中学生・高校生の皆さんは、勉強していて「自分の世界を広げることができている」実感があるでしょうか。
もしかすると、そんな実感を得ることができないとき、人は「これを今やっていて何の役に立つのだろうか」という答えのない疑問にとらわれてしまうのかもしれません。
「勉強」のために努力することは中高生の皆さんのしなければならないことですが、「勉強」を「世界を広げる実感」につなげられないことは、皆さんの責任ではありません。それは、学校や、塾で教えている私たち講師のすべき仕事であり、責任であると私は思っています。